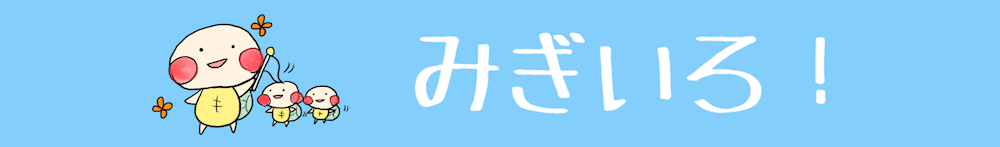これは、愛がもたらす悲劇の連鎖ー病に至るまでの恋の物語
映画公開を約1か月後に控えたタイミングで発売された、『恋に至る病』のスピンオフ小説、『病に至る恋』
間違えて購入してしまう人もいそうなタイトルですね笑。
寄河景の幼少時代が描かれるということで、ワクワクしながら本を読み進めてみました。
ページ数もそこまで多くなく、気軽に読めるので興味のある方はどうぞ。
この記事は、本編の重大なネタバレを含んでいます。
関連記事:恋に至る病の考察・解説|ラスト4行と消しゴムの意味、宮嶺は景の特別だったのか【ネタバレ】
病に至る恋 構成
- 病巣の繭
- 病に至る恋
- どこにでもある一日の話
- バタフライエフェクト・シンドローム
病に至る恋は4本の短編集です。
「病巣の繭」は、寄河景が5歳の時に保育園で起きた出来事を、寄河景の母親の視点で描いた短編。
「病に至る恋」は、ブルーモルフォのプレイヤーとなった高校生2人がゲームにのめり込んでいく様子をより詳細に描いた短編。
「どこにでもある一日の話」は、高校生で付き合っている景と宮嶺の他愛のないデートの様子を描いた短編。
そして「バタフライエフェクト・シンドローム」は、もし自分の異常性に気付いた景が小学校に通うのをやめていたら?という、並行世界のような設定のお話です。
話のボリュームとしては、3:5:1:1。前半の2作品がメインですね。
病巣の繭 感想・ネタバレ
私が、『病に至る恋』を読みたいと思った一番の理由は、この短編です。
いったい寄河景はどのようにして、あそこまで他人を操れるようになったのか。
その過程を見たくて、ワクワクしながらページをめくったのですが、その答えは驚くものでした。
そう、寄河景は5歳の時に既に周りの人間を意のままに操れたのです。
もっというと、両親の喧嘩をあいうえおボードを使って上手に止めていたのは、2歳の時。凄すぎますね。
寄河景の母親は、景が「ギフテッドなのかもしれない」と考えていますが、まさに天から与えられた才能といえるでしょう。
つまり失敗や成功を重ねる中で少しずつ上手く他者を操る方法を身に付けていったのではなく、最初からほぼ意のままに操れたということ。
おいおい、それはやりすぎだろと思いましたが、そこが寄河景らしくもあります。
さて、寄河景が5歳の時のターゲットとなったのは保育士の浪川先生、そして寄河景の母親を目の敵とする橘くんママ、そこに巻き込まれたのが橘くんです。
事の発端は、橘くんママの悪意ある行動。
その後に起こったことは、寄河景の母親が整理してくれました。
まず、浪川先生がやってくる。浪川先生が景を気に入り、目を掛けてくれるようになる。浪川先生は景をこまやかに見てくれる。そんな中で私は景が不自然な怪我をしていたり、おかしな様子をしているのに気がつく。私はそれを橘くんのせいだと疑う――。
しかし、そのうちに橘くんは保育園に来なくなる。あとから、橘くんが保育園に来なくなったのは、浪川先生による虐待があったからだと分かる。その虐待についてはおゆうぎ会で発覚し、浪川先生は責任を取って、園を辞める決断を下す。橘くんは浪川先生に与えられたトラウマで園に来られなくなり、辞めてしまう……。
そして、私は結果的に、抱えていた全ての問題を解決する。
本編で根津原のいじめがなくなり、宮嶺の小学校生活が平穏になったように、全ての問題が解決しました。
正直なところ、読み進めている段階では、橘くんママが死んでしまうんではないかと思っていましたが、さすがに保育園の段階でそこまでには至らなかったですね。
ある日、不自然な「痣」ができてから、物語が進行していくのがいかにも寄河景らしいですね。
この「痣」は、宮嶺の消しゴムがなくなったこととリンクしているような印象を受けました。
どうして景をいじめていたはずの橘くんが、景に対して怯えていたのだろう。今更罪悪感に目覚めたということだろうか?腑に落ちない。
それら全ての疑問を解決する説が、一つだけある。
初めから景は橘くんにいじめられてなんかいなかったのだ。
寄河景に対する、母親の疑念はおそらく正解でしょう。
本編でも寄河景は、公園でわざと怪我をして宮嶺の気を引いています。自らの身体に「痣」をつけることにためらいはないでしょう。
寄河景に操られてしまったのは浪川先生。妊娠していたお子さんがなくなったことで、心が弱っており、マインドコントロールされやすい状態にはあったと思います。
それでも、
「景ちゃんのお陰で、私はもう一度生きる気力が出てきたんです!景ちゃんの為なら、私は何も惜しくないから!」
という浪川先生のこの言葉にはぞっとしましたね。
5歳の子供に大人が、ここまで翻弄されてしまうのか。
景を自分の娘のように可愛がっていたのだとは思いますが、魅了され過ぎです…。
この一件で、一番かわいそうなのは橘くんですね。最初は景と仲良く遊んでいただけなのに、いつの間にか浪川先生に虐待され、景に怯えるようになってしまった。
橘くんママの素行の悪さが引き起こしたとはいえ、5歳の子供にはトラウマです。
もう1点、この短編を読んでいて気になったのは、寄河景は決して完璧ではなく、その本性を周りに見抜かれているということ。
本編では小学校の時の女友達からも恐れられていましたが、スピンオフである本編でも母親にかなりの疑念を抱かれていました。しかも、ほぼ正解に近いであろうまでに。
「騙されていることを相手に気付かせないのが一流の詐欺師」
みたいな言葉がどこかの漫画でありましたが、寄河景はそのレベルの完璧超人ではなく、隙もありそうです、
まあ、その隙までもが、他者を魅了させているのかもしれませんが…。
病に至る恋 感想・ネタバレ
延田臨と緋達美姫というブルーモルフォに参加した、2人の高校生が本作の主人公。
『恋に至る病』の本編を読んで、本当にこれで自殺してしまうのかな?と感じた人も多いのではないかと思いますが、この短編を読むと、「全然あり得るな」と思わせてしまうのが恐ろしいところ。
緋達美姫は「全てを失敗した女子高生」。そして、自らを「僕のようなゴミ」と表現する延田臨も似たような境遇。
どこにも希望を見いだせない僕のような人間にとっては、ブルーモルフォこそが脱出の方法だった。
本編では『周りに流されやすい人』がブルーモルフォのターゲットとなっていましたが、本作では単純に『社会的ヒエラルキーが低い人』が主人公となっていて、そこは少し残念でしたかね。
目的がすり替わっています。
さて、本編では描かれなかったブルーモルフォの具体的なミッションが、この短編では描かれます。
- ミッション二、あなたが自分の中で一番嫌っているところを挙げ、理由を述べてください。
- ミッション三、自分の嫌いなところを十個挙げてください。
- ミッション四、自分が一番誇らしいと思ったことを書く。
- ミッション五、その誇らしいと思った経験を台無しにするようなことがあるとしたら、一体どんなことだろうか。
- ミッション七、自分の知っている中で一番高い場所に行き、写真を撮れ。
- ミッション十二、身体のどこかに蝶の形の傷を刻む。
- ミッション十三、誰かのアカウントに対して罵倒の言葉を送る。
- ミッション十四、自分が十年以上大切にしてきたものを、誰にも見つからないように土に埋める。
- ミッション十六、過激な暴力描写のある映画を暗い部屋の中で観る
- ミッション二十六、代金を支払わずに店から品物を得る。
- ミッション二十八、一番起こってほしくないことを想像し、書きなさい。
- ミッション三十七、手に入らなかったもののことを考え、お前はこんな人間だからそれが手に入らなかったのだと百回唱える。
- ミッション四十、指定された場所に火を点ける。
- ミッション四十一、人生を失敗したと思うか。その失敗は自分のせいだと思うかについて答えろ。
- ミッション四十八、全ての人間関係を絶って備える。
- ミッション五十、この世界に別れを告げ、生まれ変わる。
簡単なものから、結構エグイものまであります。
「身体のどこかに蝶の形の傷を刻む」というブルーモルフォの象徴のようなミッションは12と早い段階にあります。
延田が語っていたように、かなりの苦痛を伴うもの。大半の人はここで離脱してしまうのでしょうか?
痛くて苦しかったけれど、終わってしまえばじくじく感じる痛みすら、達成感に変わっていた。
困難なミッションをクリアするほど、「ここまでやったのだから、もう抜けない」と気持ちにさせるのでしょうね。
個人的に結構エグイなと思ったのは、『ミッション十六、過激な暴力描写のある映画を暗い部屋の中で観る』
これ、内容にもよりますが、かなり精神をやられるんですよね。
あとはミッションの具体的な内容は描かれていなかったのですが、終盤に緋達がお風呂に入っていなかったことも印象的。
睡眠を取れていなかったり、心をがリフレッシュできていないと精神をやられやすくなりますよね。
ミッション二十六の万引きや、ミッション四十の放火は普通に犯罪。こうやって退路を断っていくんだと怖かったですね。
闇バイトに近いような印象を受けました。放火した後、すぐにミッション完了の通知が届いたのも恐ろしかったです。
あとは、シンプルに寄河景への印象は悪くなりました。
もともと大量の人間を自殺に導いた極悪人であることは分かっていたのですが、ブルーモルフォに関係ない人を巻き込む犯罪を導いていたのは想定していなかったです。
どういう心理でミッションを考えたんでしょうね。
読んでいて意外だったのは、想像以上にブルーモルフォがプレイヤーたちの誇りであり、心の拠り所になっていたこと。
ブルーモルフォのミッションをこなせるだけの力があれば、学校のやつらなんか取るに足らないのかもしれない。それに、今の僕はクラスタという大きな存在と繋がってもいるのだ。学校なんてちっちゃな世界でイキっている奴らなんて、少しも怖くないはずだ。
正直、ミッションの内容は、それを達成したからといって、そこまで誇らしいと思えるようなものではないと思います。
延田も途中で、
僕のようなまだ何も成し遂げていない人間のことを救ってくれるとは思えない
と疑念を抱いています。ただそれでも、
抜け出すことは出来なかった。
ここでやめたら、自分はいつまで経っても変われないままだ。
ですので、ブルーモルフォは心の支えというよりも、それ以外は選びようがないという「最後の選択肢」という位置づけに変わっていきました。
そんなことないはずなんですけどね…。
招待制で入れるシステムというのが、特別感・優越感を助長していた側面はありそうです。
ふざけるな。お前達なんか何も成し遂げてない普通の人間のくせに。馬鹿にするな。馬鹿にするな。ブルーモルフォのプレイヤーなんだぞ、こっちは。
学校で延田が暴れたタイミングでは、もうかなり精神がブルーモルフォにやられてしまっていて、痛々しかったです。
このあたりから、心理状態がかなり危険な方向に加速していきます。
こんな人生をやっていくくらいなら、ブルーモルフォで行き着くところまで行った方がマシなんじゃないか。
誰かここから出してほしい、と思った。
はじめはまともな精神だった延田の心が、ミッションをこなしていくにつれて、少しずつ壊れていく描写がリアルだと思いました。
読み進めて気になったのは、これが本物ブルーモルフォなのか、偽物のブルーモルフォなのかということ。
作品内ではその答えは明言されていませんが、ほぼ間違いなく本物のブルーモルフォだと思います。
この後の短編『どこにでもある一日の話』で、プレイヤーは写真を提出していることが明らかになります。
そのため、電車で寄河景が延田に話しかけているシーンがありますが、偶然ではなく、延田がプレイヤーだという確信を持って話し掛けているはずです。
緋達はゲームマスターと一度だけ話せたと語っていました。延田はゲームマスターと話したという認識は持っていなかったはずですが、しっかりゲームマスターと会話していましたね。
どこにでもある一日の話 感想・ネタバレ
言及する箇所がほぼない、普通の、ありふれたデートの話。
気になった個所をいくつか。
ブルーモルフォはミッションを全てこなして自ら死を選んだ人間は、次に生まれ変わるときに望む自分に羽化出来る、と伝えている。最初はそんな言葉がどれだけ響くんだろう、と思っていたけれど、意外にも最後に死のきっかけとなるのはその一言だというのだ。
自殺に導く最後の一言。緋達と延田の境遇を見ると、説得力があります。
ブルーモルフォにハマる人間の多くは、社会から孤立している。そうで無くても現状に不満を抱いている人物が多い。そういった人間が、ブルーモルフォを通して流されていき、やがて死に至る。
「流されやすい人」がブルーモルフォのターゲットのはずだが、個々を切り取ると、「社会から孤立している人」がターゲットのようにも思えてしまう。
これが寄河景の望みだったのだろうか…?
「人間に生まれ変わって、また私のような人間になって、同じことを繰り返して、結局何も変わらないの。私たちが何をしても世界は変わらなくて、全部同じことがまた起こるだけ。そうなったら、私は怖いな」
え、寄河景さん、人生何週目ですか?
寄河景が子供の頃から大人びているのは、まさか何週もしているからなのだろうか…?
「宮嶺は、いつまでもそのままでいてね。私のことを、ちゃんと追いかけてね。私が人間であるところを、ちゃんと見ていてほしいんだ。そうしたら私、きっとやり遂げてみせるから」
景の髪が、ビル風に舞い上がって蝶の羽のように広がる。出来すぎたくらい綺麗な演出に、息を吞む。
もしかすると、僕が真に寄河景に全てを捧げようと思ったのは、この時かもしれなかった。
景は羽化しようとしていた。本物のブルーモルフォに。今までの人間の殻を破り、本物の病として成熟していた。
ここは、この本の一番大事な箇所だったのかとも思いますが、正直なところあまりピンとこなかったです。
この言葉が宮嶺の心を揺らしたとは、どうも思えないんですよね。
景があの日、僕を連れ出したのは正解だったのだと思う。
彼女を失った僕が未だに思い出すのは、この時のデートのことばかりだからだ。
この短編は、これで終わっていますが、作者の方がなぜここを描こうと思ったのか、イマイチ読み解けていません…。
バタフライエフェクト・シンドローム
もし自分の異常性に気付いた景が小学校に通うのをやめていたら?
この短編は、本編とは異なり、並行世界を描いたもの。
小学校5年生の寄河景は不登校。その寄河に、宮嶺が記念品を届けに行く話。
寄河景と宮嶺の基本的な性格は本編と変わらない。
「私はね、怖いんだ。」
「私はね、みんなを動かす力があるんだ」
本編もしかりだが、寄河景の心の中は基本的に描かれない。そんな寄河景が、本心を打ち明けているかのような描写は珍しい。
「私がお願いすると、みんな私の言うことを聞くの。私がこうなったらいいなと思ったら、みんなそうしてくれるんだ。
私がこんなクラスがいいなと思ったら、その通りのクラスになる。先生の言うことをみんなが聞く、良い子のクラスにもなるし、みんなが仲の良い、絆が強いクラスにもなる。反対に、先生の言うことを誰も聞かない学級崩壊状態にもさせられる。私がそうなってほしいと思ったらそうなるんだ」
もちろん、この言葉も本心ではないのかもしれない。
でも、もしこの言葉を本当だとすると、寄河景は無自覚に人を操れるということになる。
個人的には、寄河景はものすごく計算高い悪人だと思っていたので、かなり意外でした。
だって宮嶺の消しゴムを盗んだり、わざと体に痣をつくって橘くんママを破滅に追い込む人ですよ?
それが計算ではなく、無自覚なのだとしたら…。それは本当に特殊能力ですね。
ただ、僕が思い描くブルーモルフォマスターの寄河景は、やはり極悪人であってほしいという気持ちは変わらないですね。
寄河景は何なのか。それが読み解けると思って開いた本ですが、謎は深まるばかりです。