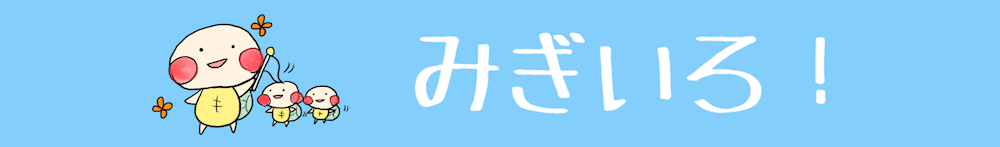私の友人が行方不明になりました。情報をお持ちの方はご連絡ください。
いやー、怖かった。怖かった。
ホラー系の映画を見るのは久しぶりだったんですが、ちょくちょくスクリーンから目をそらしながら鑑賞しました。
公開初日の8月8日に見に行ったのですが、30度を超える真夏にも関わらず、帰りの車でなんとなくクーラーを切りました。寒いなって。
あと、ここで事故ったら嫌だなと思って、いつもより安全運転をして帰りました(笑)。
書籍を買おうかずっと気になっていて、結局買わずに何の事前情報もいれずに映画を見ました。
正直なところホラー映画は苦手なジャンルなので、最後まで見るのはきついかなとも思ってました。
実際に、上映途中で退席されたお客さんもいました。
思わず声を上げそうになったシーンも何度かありました。
でもその一方で、ところどころ、妙に安っぽいんですよね。
現実でも起こり得そうなシーンは怖いんですけど、CGアニメーションもりもりのところは、「そりゃないわー」って冷静に見てしまったのであまり怖くなかったです。
特に、クライマックスのシーンは幻滅しました…。カオナシ…!?
そんな、映画「近畿地方のある場所について」を振り返ります。
映画「近畿地方のある場所について」あらすじ
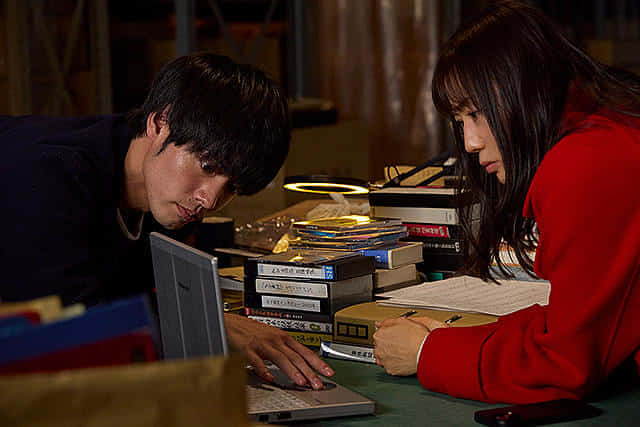
オカルト雑誌「超・不思議マガジン」の編集長・佐山が失踪した。
彼が消息を絶つ直前まで調べていたのは、幼女失踪、中学生の集団ヒステリー、心霊スポットでの動画配信騒動といった、過去の未解決事件や怪現象だった。
彼はなぜ突然消息を絶ったのか?
いまどこにいるのか?
どんな特集記事を作ろうとしていたのか?
編集部員の小沢は、女性記者の千紘と共に佐山が残した資料を探り、調査・考察を進めていくが、ある恐るべき事実に気付く。
すべての謎は「近畿地方のある場所」へと繋がっていたのだった…。
映画「近畿地方のある場所について」感想
超不思議マガジン「1週間で特集25ページ」

この物語を進める上での大きな原動力は、小沢と千紘が超不思議マガジンの特集ページを書き上げるというもの。
私は雑誌の編集をしていた経験があるのでよくわかるのですが、「1週間で特集25ページ」はやばすぎます。ムリゲーです。
千紘、よく引き受けたなと思いました。内容にもよりますが、4ページくらいの原稿を書くのにも2日はかかります。
それも、特集のテーマすらよくわかっていないような状態。
雑誌の編集の仕事をやっている人からすると、ある意味この映画で一番のホラーシーンだったのかもしれません(笑)。
VHSビデオの怖さ

この映画の怖さを演出する上で、重要な役割を果たしていたのがVHSビデオです。
序盤、地価の資料室でビデオデッキが登場したところで、懐かしいなーと思いながら見ていました。
ビデオならではの画質の荒さ、不鮮明さ、ノイズが怖さを引き立てていましたね。
実際の所、撮影した年代はそんなに昔でもなかったので、もう少し綺麗な映像が残っていてもよさそうですが(笑)。
途中でツーリングの男性が祠を訪れたシーンが鮮明で、あまり怖くなかったので、やはりVHSビデオはホラー映画には欠かせないと思いました。
序盤の中学の林間学校の集団ヒステリーのシーンは怖かったです。
リアル感がないと感じる人もいるかと思いますが、個人的にはああいった集団パニックの演出はあまり見たことなかったので。
あのシーンも、現代の鮮明な映像で見せられたらあまり怖くないと思います。
恐怖のニコ生配信「首つり部屋」

この映画で、最大級のインパクトを残していたのが、ニコ生配信の「首つり部屋」です。
あれだけの本数の首つりロープは衝撃的でしたし、子ども部屋が封鎖されていたところも、怖さに拍車をかけていました。
ニコ生の画面が「もう配信やめた方が」みたいなコメントで溢れていましたが、まさに同じ気持ちでスクリーンに釘付けでした。
具体的な場所はわかりませんが、あんな山奥も電波が通っていて、配信できるんだと気にはなりましたが(笑)。
クライマックスで伏線が回収されますが、畳に空いていた謎の穴も気味が悪かったですね。
「途切れることなく生き物を飼い続けてください」
個人的に印象に残ったシーンが、住職さんの「途切れることなく生き物を飼い続けてください」というセリフ。
住職さんがお祓いの途中で嘔吐したところは安っぽかったのですが、途中で子どもたちが「ましらさま」で遊ぶシーンで「みっがわり」「みっがわり」と連呼していたことで妙にリアル感がありましたね。
それにしても、「みがわり」と分かっていて生き物を飼うのはつらいところがありますね。
取材していた大学生の目黒君が、メダカ10匹を飼った後、「猫が5匹死んだ」とさらっと言っていたところが衝撃的でした。
編集部員の小沢くんが憑りつかれたシーンで、金魚がぷかぷか浮いていた演出も怖かったですね。
スクリーンいっぱいに金魚の死体が強調されていたシーンよりも、その少し手前で一瞬だけ水槽が映った時に、金魚の姿がなかったのが怖かったです。
あと、編集長・佐山が夜逃げした先の富士山の家で、大量の動物の死骸の中で、オウム(インコ?)だけ生きていたのも印象的。
鳥は長生きするんだなと。
リアルな怖さと安っぽさと

監督がトラウマ級に怖い映画を目指したと言う本作。
冒頭に書いた通り、実際に怖かったですし、「もうやめてー!」と心の中で叫ぶシーンが連発でした。
ただその一方で、安っぽいなと感じてしまうシーンも多くあったのは残念でした。
ホラー映画に何を求めるのかで、人によって感じ方は異なると思いますが、個人的には「現実でも起こりうるかもしれない」というようなシーンに最も恐怖を感じるんですよね。
その一方で、「視覚的に怖いだけのシーン」は論理的整合性に欠けるというか、現実感が感じられないためか、恐怖感が薄れてしまいます(あくまで個人的には)。
例えばですが、
- 映画冒頭で編集長・佐山の両目から血が流れるシーン、
- 編集部員・小沢が意識を失って憑りつかれたところで後ろの影の形が明らかに違うシーン
こういった場面は、「作り物感」を感じてしまい、冷めてしまいました。
あとは大学生・目黒宅のベランダに謎の女性がいるシーン。この女性・背が高すぎませんか?(笑)
窓の一番高いところまで手が届いているので180センチ以上はあるかと思います。こういったリアル感のなさが気になってしまうんですよね。
あとはなんといってもクライマックスのましらさま(?)登場シーンです。
「カオナシやん」って見てる全員が心の中でツッこんだのではないでしょうか。
あそこのCGはもう少し何とかならなかったんですかね…。
小沢に飛びつく大量の目ん玉も含めて、リアル感がなさ過ぎて恐怖感ゼロでした。
とはいえ、この作品のテーマが「フェイクドキュメンタリー」のようなので、そういったところを指摘するのはナンセンスとも思っています。
「近畿地方のある場所」は実際にどこ?
こちらは実在の地名を指しているわけではなく、意図的に曖昧さを残したまま物語を紡いでいる作品です。
しかしその“ある場所”が具体的にどこか(例えば「奈良県の◯◯」など)は、作中でも明言されず、むしろその正体の不確かさが恐怖を引き立てています。
「近畿地方のある場所」とは、意図的にぼかされた架空の場所であり、実在の地名や地理的特定を避けて、読者・観客自身に想像させるホラー演出の一部となっています。