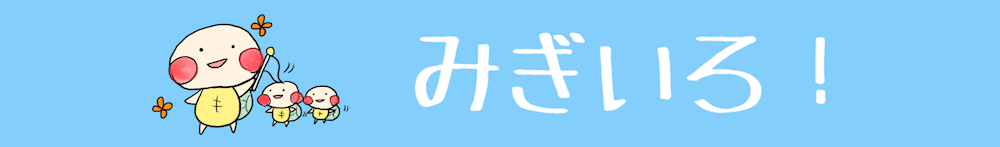「ちょうどよくしあわせなんだ」
もう若くはない男と女の、静かに滾るリアルな恋。
『平場の月』(朝倉かすみ)は、50代の男女の再会と恋を描いた、大人のための恋愛小説です。
病や孤独、過去の痛みを抱えながらも「ちょうどよくしあわせなんだ」と語る須藤と、彼女を支えようとする青砥――。
派手な奇跡やドラマはなくても、日常の中にある“じんわりとした幸福”が心に残ります。
この記事では、『平場の月』のあらすじや登場人物、タイトルの意味を解説します。
大人の恋愛小説や「人生の後半に訪れる恋」に関心のある方に、ぜひ手に取っていただきたい一冊です。
平場の月 あらすじ

朝霞、新座、志木――。家庭を持ってもこのへんに住む元女子たち。
元男子の青砥も、このへんで育ち、働き、老いぼれていく連中のひとりである。
須藤とは、病院の売店で再開した。中学時代にコクって振られた、芯の太い元女子だ。
50年生きてきた男と女には、老いた家族や過去もアリ、危うくて静かな世界が縷々と流れる――。
心のすき間を埋めるような感情のうねりを、求めあう感情を、生きる哀しみを、圧倒的な筆致で描く、大人の恋愛小説。
平場の月の意味

作者の朝倉かすみさんはタイトルは最初から決めていたといいます。
"平場"とは、ごく一般の人々のいる場といった意味。
「言ってしまうと格好悪いんですが、"地上の星"みたいなことを考えていました。平場でうまく生きるって難しいということがひとつ、もうひとつは比喩的な意味で、足元ばかり気にして歩くのでなく、もっと見上げてほしい、夢を見てほしいという気持ちがありました」
また、光文社のYouTubeのインタビューでは、「平場」という言葉を使った理由について、このように語っています。
「私はお笑いが好きで、お笑い芸人の人たちが、ネタをやる劇場以外のところでテレビとか出るところを平場っていうんですね。それで平場という言葉を覚えて、だから一般的な場所という意味で、何とかして使いたいなとは思いました。」
平場の月の制作背景
編集者に「次はどんなテーマで書きましょうか」と尋ねられた朝倉かすみさんは、「『世界の中心で、愛をさけぶ』みたいなものがやりたい」と答えたのだといいます。
「あの本をたまたま読み返したら、主人公の男の子がすごく純粋で、改めていい本だなと思って。あんなに若い時にそこまで思える相手と出会ってしまったら、それは大変ですよね。ただ、彼らはまだ働いてもいないし、恋愛に集中できる年頃。もしもこれが仕事があって稼ぎがある大人だったら、また違う恋愛になるかもしれない、と思ったんです。自分自身、年齢的に周囲に大病に罹ったり亡くなったりする人が増えてきていますし、じゃあ大人の『世界の中心で、愛をさけぶ』をやってみようと思いました」
平場の月 ストーリー
小説『平場の月』は第1章で先に結末が明かされる構成となっています。
一「夢みたいなことをね。ちょっと」
昼休み、印刷会社で働く青砥健将は、同僚の安西から中学時代の同級生・須藤葉子(通称ハコ)の訃報を知らされる。
彼女が亡くなったのは一ヶ月前。葬儀は行われなかった。青砥は「おれのところには連絡がなかった」と胸に痛みを覚える。
その足で彼は花屋を訪れ、供えるための花を選ぶ。須藤の好きだった花や、アパートの駐車場に植えていたハーブの草を思い出しながら、二人で過ごした時間をたぐる。
ある日の深夜、べランドの窓から顔を覗かせた彼女の表情は、月のようだった。
「夢みたいなことをね。ちょっと」と須藤は微笑み、何か儚い願いを胸に秘めていた。
二「ちょうどよくしあわせなんだ」
青砥は50歳を前に、胸やけやげっぷの症状で受診し、胃の内視鏡検査を受けた。
「念のため」という言葉に怯えながら検査を終えると、生検が必要だと言われ、結果を待つ不安を抱えることになる。
空腹を感じつつ病院の売店に立ち寄った青砥は、会計の列に並ぶと、レジ係が中学の同級生・須藤(ハコ)であることに気づき、さらにもう一人の同級生・ウミちゃんとも再会する。
思いがけない「ミニ同窓会」に驚きつつも懐かしさを覚える青砥は、二週間後に再び病院に来る約束を口にする。
その後、青砥は中学時代を思い出す。仲間4人でつるんでいた頃、友人の江口が須藤に告白した。
須藤はきっぱりと「いやです」と断り、「江口くんだからじゃなく、今は誰とも付き合う気がない」と告げる。
それから少しして、青砥も須藤に告白したが、断られた。須藤の頬に、自分の頬をあてたが、須藤は平然としているようだった。
そして50を前にした今、須藤は今が「ちょうどよく幸せなんだ」と語り、「景気づけ合いっこしない?」と青砥と二人で会う約束をする。
三「話しておきたい相手として、青砥はもってこいだ」
青砥と須藤は、LINEのやり取りから「互助会」と称して二日後の土曜に駅前の焼き鳥屋で会うことになった。
青砥にとっては、生検の結果待ちという代わり映えのしない日常に小さなひびを入れる出来事でもあった。
実際に顔を合わせた二人は、服装や仕事の話など、当たり障りのない会話から始めるが、次第にそれぞれの生活や過去に踏み込む。
須藤は証券会社を結婚退職後、夫に先立たれて地元に戻り、2年前から病院内の売店で働いていることを語る。
一方、青砥は妻子に去られ、母の介護を経て印刷会社に転職した過去を打ち明ける。
お互いに中年になった今の孤独や、地元に舞い戻った経緯を共有しながら、再会の意味を少しずつ確かめ合う。
次の土曜日は須藤のアパートで飲むことに。青砥がアル中だったことについて打ち明けると、須藤も「わたしも沈みそうになったこと、あるよ」と、新しい男にお金を使い込んでしまったことを語る。
互いの人生の経緯を知ることで、ただの同級生の再会から少しずつ踏み込んだ関係性が生まれる。
そして須藤は、大腸検査を予定していると語る。
四「青砥はさ、なんでわたしを『おまえ』って言うの?」
青砥は「生検の結果、異常なし」と告げられ、大きな安堵を覚える。
病院を出て自転車を走らせる途中、かつての同級生ウミちゃんと再会。昔ディスコで会った頃の記憶や、軽薄に振る舞っていた自分を思い返す。
会話の中でウミちゃんは、青砥の元妻や地元での噂についても触れ、青砥は離婚に至るまでの経緯を振り返る。
妻の「相談癖」が原因で夫婦仲が悪化し、長年の結婚生活は終わりを迎えていた。須藤は検査の結果、手術が必要になった。
五「痛恨だなぁ」
須藤は内視鏡検査で腫瘍を確認され、「悪性の可能性が高い」と告げられる。
本人も直感的に「ついに来た」と受け止め、がんを現実のものとして意識し始める。診断の後は患者向けのガイド本を買ったりして、自分なりに気持ちを整理しようとする。
ストーマ(人工肛門)の造設が必要になったことに青砥は衝撃を受けるが、須藤は「治療なんだよ。出口を変えるだけ」と冷静に受け止めようとする。
青砥は「治るのかどうか」を知りたいが、須藤は核心を語らず、二人の間には「親友でも恋人でもない」微妙な関係性が流れる。
病気の話題になると繊細なムードが生じ、青砥は須藤を大切に思う気持ちを募らせていく。
須藤は仕事についても、治療で迷惑をかけると考え、勤務先の売店を辞める。
入院の前日、青砥は須藤を抱き締め、体を重ねる。
9月最初の日曜日、青砥は須藤を見舞いに病院に行き、ネックレスを贈る。
六「日本一気の毒なヤツを見るような目で見るなよ」
須藤は退院後、人工肛門(ストーマ)の装具の扱いに苦労し、失敗や臭いへの不安で心身ともに消耗していた。
しかし、ストーマ外来でベテラン看護師と対話し、セルフケアの再確認を経て、少しずつ落ち着きを取り戻す。
術後の化学療法が必要であり、リンパ節転移も判明したが、須藤はそれを「大きな山」として前向きに受け止め、むしろ気持ちを立て直していった。
青砥は須藤を支えようと学びつつも、彼女と妹が当事者で自分は外側にいるという感覚に複雑さを抱く。
二人は日常の買い物や会話を重ねる中で、病気とともに生きる現実を共有していく。
七「それ言っちゃあかんやつ」
抗がん剤治療を終えた須藤はアパートに戻り、一人暮らしを再開する。
青砥は送り届けたものの、須藤が「元の生活」にあっさりと戻っていく様子に寂しさを覚える。
三か月間の濃密な同居生活を経て、青砥は「これからも須藤と暮らす」と当然のように思っていたため、置き去りにされたような感覚に陥る。
一方須藤は病後のリハビリを兼ねた「チョコチョコ買い」など、自分の生活を楽しんでいた。
その後、須藤は青砥の職場に顔を出したり、家庭菜園のようにローズマリーや豆苗を育てて青砥に披露するなど、徐々に日常を取り戻していく。
やがて病院売店での復職の話が持ち上がるが、ストーマや体力の問題への不安も隠せない。
青砥は「試しに自分の会社で働けばいい」と提案し、須藤は乗り気になる。
二人は一緒に池袋へ買い物に出かけ、仕事に適した服を探すが、結局スニーカーだけを購入する。
須藤は前向きに「働く日常」へと歩みを進めるが、青砥は彼女と暮らした日々の濃さを忘れられず、どこか釈然としない思いを抱え続ける。
八「青砥、意外としつこいな」
青砥は、母の習慣である「予定を書き込むカレンダー」を前に、自分と須藤の関係の時間感覚を強く意識する。
須藤に「一年会わない」という条件で別れを保留されたが、カレンダーに日付を書き込んだ途端、その「一年」の長さと重さに圧倒される。
表面的には「まだ繋がっている」と思おうとする一方、実質的には別れているのではないかという不安が膨らんでいった。
青砥は「自分がいいと言っているのだから、それでいいじゃないか」と須藤に伝えたいが、それが須藤の本心を尊重しない、男臭い強引さに通じることを自覚している。
どうすれば須藤に「いい」と言わせられるのか葛藤する。
約束の日、池袋のホテルに行ったが須藤は現れず、偶然出会った旧友・江口の「花嫁の父」としての姿を目にして、現実の重みを痛感する。
青砥にとって「一年会わない」という取り決めは、結局「別れの既定路線」に近いものだった。
夏の日々はむなしく過ぎ、LINEを送っても既読がつかない現実に打ちのめされる。
秋になると、別れのきっかけは自分が早まって「結婚」を持ち出したことではないかと気づく。須藤の「ぶちまけ」は、青砥を否定するものではなく、自分自身を嫌悪していたがゆえのものだったと理解しはじめる。
青砥は、須藤の苦しみを和らげていたのは自分との関係だったのではないかと思い至る。
九「合わせる顔がないんだよ」
須藤の死を知った青砥は、喪失の現実に直面する。
日常の中に残された須藤の痕跡(寝床、サンダル、冷蔵庫のネクターや貯金箱など)に触れることで、かつての生活が鮮やかに蘇る一方、それがもう二度と戻らない事実に打ちのめされる。
須藤のアパートを訪ねると、菜園は更地となり、そこで偶然須藤の妹と再会する。
妹から、須藤が二度目の手術や腹膜播種を経て、最期には「青砥に合わせる顔がない」と言って逝ったことを聞かされる。
青砥は菜園を掘り返し、土の中から須藤が残した封筒とネックレス、そして自宅の合鍵を見つける。
それは、彼女が最後まで青砥を思っていた証だった。
過去のささやかな場面や須藤の声が次々と胸に去来し、彼は「結婚なんてしなくてもよかった。
ただ一緒に生きられればよかった」と痛切に悔やむ。
須藤を失った世界は色を失い、空虚さが押し寄せるが、同時に彼女との関わりの「根の深さ」を実感する。
平場の月 登場人物
『平場の月』の登場人物は、いずれも「特別ではない人生を生きる人々」として描かれています。
青砥 健将(あおと けんしょう)
主人公。50歳前後の男性。
地元の印刷会社で働く中年男性で、独身。かつて結婚していたが、妻子に出て行かれた過去がある。母親の介護のため地元に戻り、現在は実家暮らし。
物語の現在では体調不良から病院を受診し、「念のため」と言われた検査で胃に「おできのようなもの」が見つかり、生検結果を待つ身となっている。死や老いへの不安を感じつつも、どこか達観したような諦念を抱いている様子が描かれる。
須藤 葉子(すどう ようこ)/通称「ハコ」
ヒロイン的存在。青砥の中学時代の同級生。
須藤葉子(ハコ)は、青砥の中学時代の同級生で、芯の強さと揺るがない意志を持つ女性。30歳で結婚・退職するも41歳で夫を亡くし、子どももなく地元へ戻って総合病院の売店で働いている。派手さはないが、自作の菜園やミルクコーヒーの時間など日常の小さな幸せを大切にし、「ちょうどよくしあわせ」と語る感性の持ち主。青砥との再会を機に、お互いの悩みを語り合う「互助会」を提案するなど、人との距離を大切にしながらも支え合いを求める成熟した人物である
ウミちゃん
中学時代の同級生で、現在も青砥・須藤と交流がある女性。あだ名で呼ばれており、本名は不明。情報収集・拡散力が非常に強く、地元の人間関係の「情報屋」のような存在
安西(旧姓:橋本)
青砥・須藤の中学時代の同級生。現在は青砥の会社でパート勤務している主婦。夫は痛風を患っており、日々弁当を作るなど家庭をしっかり支えている。社交的で噂話が好きな一面があり、須藤の訃報を青砥に伝える役目も担っている。
その他の登場人物
- 江口(えぐち):青砥の中学時代の友人のひとり。学生時代は青砥・森・後藤と4人組でつるんでいた。須藤に好意を抱いて告白したが、あっさりと断られる
- ヤッソさん:青砥の職場の同僚。社交的な性格で、飲み会で場を盛り上げる
- 青砥の母親:要介護状態で施設に入所中。かつてはいなり寿司をよく作っていた。
- 青砥の父親:故人。健康のためのウォーキング中に急逝した。
平場の月 感想
この本を読んでいると、「ああ、大人になるってこういうことなんだよな」と何度も思わされました。
『平場の月』は、いわゆる劇的な恋愛小説でも、人生をやり直す感動のドラマでもないんです。
どこにでもいそうな50代の男女が、偶然の再会をきっかけに、少しずつ心を通わせていく。ただそれだけの話。
でも、その“ただそれだけ”が、妙に心に刺さりました。
青砥と須藤は、若いころ同級生だった二人。お互いに色々なものを失い、「平場(=特別ではない場所)」に戻ってきた今、再び顔を合わせます。
最初はただの世間話みたいなやりとりなのに、話が進むにつれて少しずつ心の奥の重たい部分が出てくるんですよね。昔の恋の記憶とか、人生の痛みとか、そういうものがゆっくりと滲み出てきて、読んでいるこちらも自分の過去を思い返さずにはいられません。
須藤が「ちょうどよくしあわせなんだ」と言う場面があるんですが、これがとても印象的でした。
派手なことや大きな夢じゃなくても、ミルクコーヒーを飲みながら歩く時間や、小さな菜園の世話をする時間の中に“幸福”がある――その感覚が、30代の自分にも少しわかるようになってきた気がします。
若い頃は「もっと大きな幸せ」を追いかけていたけど、今は「ちょうどよさ」の尊さが身にしみるんですよね。
そして何より、この物語は「結末がわかっているのに希望を抱かずにいられない」小説です。
須藤が亡くなってしまうことは序盤からほのめかされているのに、「もしかしたら」と思いながら読んでしまう。
でもその希望が叶わなかったときの喪失感と、「一番つらいときに、そばにいてほしかった」「いてあげたかった」という想いが、静かに胸を締めつけます。
ラストで彼女の心の奥を想像すると、まるでボディブローのような切なさが押し寄せてきました。
大人になると、人生は「キラキラ」ではなくて「じんわり」になっていくものなんだと思います。『平場の月』は、そんな“じんわり”の尊さを教えてくれる物語でした。
派手さもなく、すごい奇跡も起こらないけれど、「平場」にいる私たちの生き方を静かに肯定してくれる一冊です。
読み終えたあと、誰か大切な人に「会って話したい」と思わせてくれる本でした。